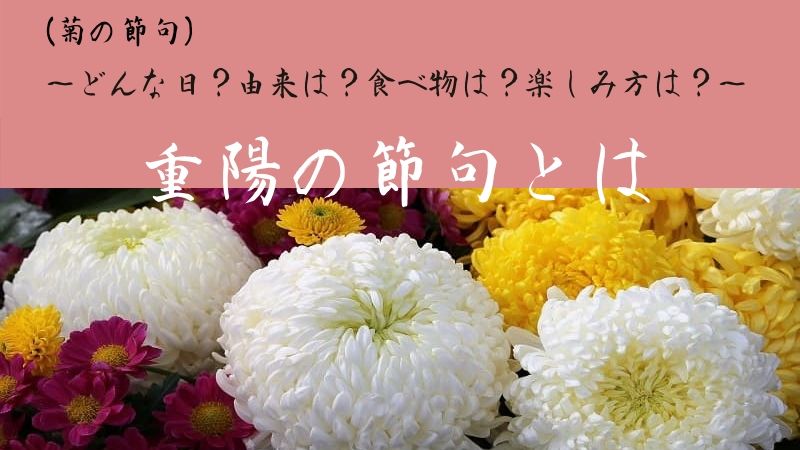
✓重陽の節句ならではの食べ物は?
✓どのように過ごすの?
このような疑問を解消します。
秋、9月には「重陽の節句」という行事があります。あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、桃の節句や端午の節句と並ぶ五節句のひとつ。別名「菊の節句」とも呼ばれています。
現代では他の節句に比べると知名度は低いのですが、実は昔は五節句の中で最も重要とされていました。いったい重陽の節句とはどのような行事なのでしょう。
この記事では、重陽の節句の意味や由来、時期はいつなのか、行事食や楽しみ方までご紹介します。
このページの目次
重陽の節句はいつ?

五節句「重陽の節句」は毎年9月9日。
その歴史は古く、元々は旧暦9月9日にお祝いされていた年中行事です。新暦に直すと10月中旬から下旬頃になるところですが、重陽の節句は現在の暦においても「9月9日」に行われます。
ただ、地域によっては新暦に合わせて行われるケースもあります。重陽の節句では菊、栗、ナスといった秋の収穫物が使われるため、新暦の9月9日では収穫時期がズレてしまうからです。
重陽の節句が他の五節句と比べて影が薄くなった原因は、この旧暦と新暦による違いとも言われています。
重陽の節句とは【意味と由来】

重陽の節句は菊が象徴的なこともあって、別名「菊の節句」とも呼ばれています。邪気を祓う力が宿り、寿命が延びるとされている菊を使い、不老長寿や繁栄を願う行事としてお祝いされてきました。
中国から伝わってきた「五節句」の最後を締めくくる節句です。
五節句とは
季節の変わり目に生まれやすい邪気や厄を払い、無病息災を願う五つの神事。
- 人日(七草がゆ)・・・1月7日
- 上巳(桃の節句)・・・3月3日
- 端午(菖蒲の節句)・・・5月5日
- 七夕(星祭)・・・7月7日
- 重陽(菊の節句)・・・9月9日
現代とは逆に、昔は最も盛んにお祝いされていた節句でした。
旧暦9月9日は現在の10月中旬頃でちょうど”菊”が見頃を迎える時期。ところが、現在の9月9日はまだ秋らしさが薄く、菊の盛んな時期とも若干ズレがあります。
旧暦から新暦に変わっても変わらず9月9日にお祝いされていることで、他の節句よりも季節感が合わなくなってしまうことに。結果、徐々にその存在が薄くなってしまいました。
奇数は縁起が良い!9月9日は最もめでたい日だった!
起源は他の節句と同じく中国から伝わってきた五節句です。「1月7日の人日(元は1月1日)」「3月3日の上巳」「5月5日の端午」「7月7日の七夕」「9月9日の重陽」を指しており、五節句は全て同じ「奇数」が連なっています。
POINT
古代中国において「偶数は縁起の悪い”陰数”」「奇数は縁起の良い”陽数”」。
中でも1から10の間で一番大きい9は最高に縁起の良い数字だと考えられていました。そんな9が2つ重なる9月9日を「重陽(陽数が重なる)」と呼び、最も縁起の良い日として盛大にお祝いされていたのです。
ただ、奇数が連なるめでたい日である反面、災いに転じやすいとも考えられていたのだとか。そのため、お祝いと共に厄払いの儀式も執り行なわれていました。
重陽の節句といえば「菊」!
重陽の節句は別名「菊の節句」とも呼ばれており、菊が象徴的な行事となっています。
古来より中国では菊は薬草としても用いられ、長寿をもたらす花として大切にされてきました。菊のおかげで少年のまま700年生きた「菊慈童(きくじどう)」という故事も存在するほど。
そこで、中国では9月9日に菊を浮かべた菊酒を飲んで邪気を祓い、長寿を願う風習が生まれたといわれています。
日本に伝わってきたのは平安時代
重陽の節句が海を渡って日本に伝わって来たのは平安時代。平安貴族が日本に伝来したばかりの珍しい菊を観賞しながら、菊酒を飲む宴が催され、厄払いや長寿祈願が行われていました。これを、宮中行事「重陽の節会(せちえ)」と呼びます。
また、宮中の女官の間では「菊の着綿」という風習が流行ったのだとか。前日の晩に菊の花を綿で覆っておき、菊の香りと朝露を含ませた綿で体を拭くことによって、長寿になるとか若返ると信じられていたようです。
江戸時代になると、式日(祝日)とされていた五節句となり、庶民の間でも盛大にお祝いされるようになります。
しかし、明治以降に旧暦から新暦に変わると、季節感にズレが生じたことなどが原因で徐々に廃れてしまうことに。
重陽の節句で食べる行事食

重陽の節句は秋の収穫祭とも関係のある行事のため、祝い膳には秋の味覚がよく使われています。
栗ごはん
重陽の節句はちょうど栗の収穫期と重なっていたことから、江戸時代に栗ごはんを食べる風習が生れました。そのため、菊の節句以外にも庶民のあいだで「栗の節句」とも呼ばれていたようです。
秋茄子
秋ナスを使った料理も定番メニュー。「おくんち(9日)に茄子を食べると中風にならない」という言い伝えもあり、焼き茄子や茄子の煮びたしなど、茄子を使った料理を食べるようになりました。
中風とは
脳血管障害の後遺症のこと。半身不随、片麻痺、
食用菊
昔から菊は食用としても親しまれていました。食用菊は観賞用の菊を食用に品種改良したもので、苦味が少なくほのかな甘みを感じられるのが特徴。

現在でも食用菊をおひたしやお吸い物にして食べられています。花びらのみのお吸い物、おひたし、和え物、天ぷらなどに使われているのは主に大輪種。刺身のつまに使われているのは黄色い小輪種です。
重陽の節句の楽しみ方

現在では馴染みが薄い節句となってしまっているため、何をする行事なのかよく分からない方も多いのではないでしょうか。最後に重陽の節句の楽しみ方をご紹介します。
菊酒
菊酒とは、その名の通り菊の花びらを浸したお酒のこと。お酒を入れた杯に菊の花びらを浮かべ、不老長寿を願って楽しまれていました。古くは平安時代の頃から行われてきたお酒。
本来は漬け込んだ菊の花びらを使いますが、食用菊の花びらを浮かべるだけでも雅な雰囲気を味わえます。
被せ綿/着せ綿(きせわた)
「被せ綿(着せ綿)」とは、宮中の女官たちが好んで行っていた日本独自の風習。前日の夜のうちに菊に綿を被せて、翌朝の朝露や菊の香りがしみ込んだ綿で体を清めるというもの。被せ綿で体を清めると長生きできると信じられていました。
本来は「赤い菊には白い綿」「白い菊には黄色い綿」「黄色い菊には赤い綿」を被せるのが正式です。
菊湯・菊枕
重陽の節句の象徴である菊を使った「菊湯」や「菊枕」もおすすめ。菊湯とは、その名の通り菊を湯船に浮かべたお風呂のことで、現在でいうハーブバスのようなもの。菊枕とは、乾燥させた菊の花を詰めた枕のこと。
どちらも日々の疲れを癒すのにピッタリな風習です。菊を使った雅なアロマテラピーを楽しんでみてはいかがでしょうか。
9月9日は重陽の節句を意識して過ごしてみよう
重陽の節句は端午の節句と並ぶ五節句のひとつでありながら、一般的にはあまり知られていない行事となっています。でも、昔は最も重要とされており、盛大にお祝いされていました。
奇数は縁起が良い陽数であり、その奇数が並ぶ日をお祝いしたのが五節句。なかでも、陽数の最大値である「9」が並ぶこの日は非常におめでたい日と考えられていたのです。
菊の節句とも呼ばれる通り、行事食、お風呂、枕など、様々な形で菊を取り入れているのも特徴。長寿の象徴であり、邪気を祓うとされる菊のパワーにあやかってみるのもいいと思います。
今年の9月9日は菊や秋の食材を使った料理を用意して、重陽の節句をお祝いしてはいかがでしょうか。
